北欧切手研究会の会報『FINDS』271号の編集が完了し、印刷へ回りました。
あとは出来上がったのが送られて来るのを待つだけなので、ヤレヤレといった感じですね。
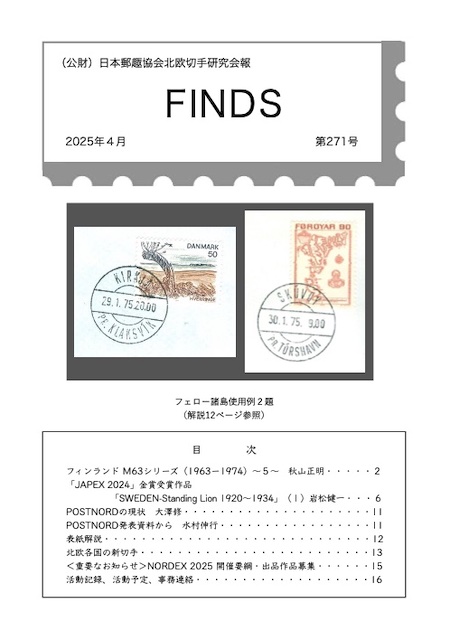
と、言いたいところではあるのですが、続けて鉄道切手研究会の会報編集を始めねば・・・。
まぁ、こちらは編集委員会方式なので多少は気が楽ではありますが、委員会を開いて議論する手間がかかります。
それにしても、今のDTP環境の作業工程は楽ですよね。
途中で生じた編集の手直しなども、パソコン一つでアッという間に終わります。
昭和の末期頃までは、紙と鉛筆のアナログでしたからねぇ・・・。
日常的に編集することが業務の一つではあったのですが、原稿はもちろん手書き。
本のレイアウトは、表紙から奥付までの全ページを紙の割付表に図版部分や文字部分を割付。
その割付表と原稿をセットで、印刷屋さんに入稿でした。
びっくりしたのは、今でもよく覚えていますが、昭和63年のある日のこと。
落札業者との打合せで「先生は何で原稿書かれています?」というので、「一太郎ですけど」と返事をしたら、「じゃあ、フロッピーで下さい」って言うんですよ。
「は?フロッピーですか。そんなものでどうするの?」と聞くと、「岐阜県(僕が居たのは福井県)まで持って行かなければならないのですが、今はフロッピーを読み込ませると、写植機と連動して文字列が組めるんです」と。
当時は、まだ写植の時代でしたから、説明を聞いてもさっぱり理解できませんでしたね。
「フロッピーのデータから印刷ができる?」
「なんのこっちゃ」みたいな感じです。
ちなみに、フロッピーは5インチ2DDでした。
平成7年の阪神淡路大震災の復興関係の調査で兵庫県に派遣されていた時に、京都市から派遣されていた同僚が、自らパソコンでDTP編集しているのを見て、これまたビックリ。
彼の影響で自分でも使い始めたのが、QuarkXPressでした。
で、仕事中に閃いたのが「これってリーフ作りに使えるじゃん」と。
ですから、僕のリーフにはQuarkXPressで作られたのが沢山ありますし、今でもデータは残してあります。
ところが、MacがOSXに移行した時にQuarkXPressは対応が遅かったのです。
そこに乗り込んできたのが、AdobeのInDesignで僕も渋々InDesignに乗り換えました。
もともと仕事で使い始めたDTPソフトですが、今ではすっかり郵趣専用です。